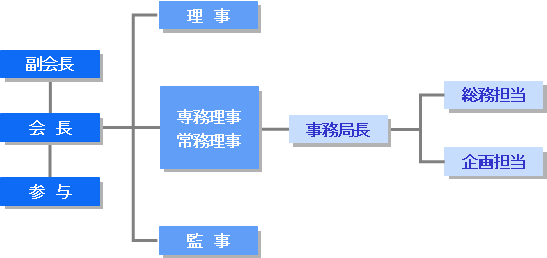会長ご挨拶 |
 |
公益社団法人 日本河川協会会長 |
地球は、川や海、湖のように液体の形で水が表面に存在する太陽系の中で唯一の星、多分、宇宙の中でも非常に珍しい星です。液体の形で水が地球表面に存在するおかげで、人間を含めて多くの生物が生息しています。水は、常に同じ場所に留まっているのではなく、太陽エネルギーによって海水や地表面の水が蒸発して雲となり、地球の重力によって雨や雪となって地表や海面に降り、地表に降った雨や雪は流下して川となって海に至り、また蒸発するという循環を繰り返しています。人間は、主としてこの水循環のなかの川や湖の水を飲料水や農業用水、工業用水に利用するとともに、美しい水の景観や水辺の自然とのふれあい等によって豊かな感性や文化を育むなど、様々な形で恩恵を受けてきています。 |
| 国民にとって安全かつ快適で自然豊かな川のあり方を探求し、河川に関する情報の交流と知識の普及に努めるとともに、河川整備及び関連諸活動を支援することにより河川文化の発展に寄与し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的にしています。 |
1.河川に関する新たな知見や情報などの調査・資料収集を行い、広く一般に成果を公表する事業 【調査事業】 【河川に関する意見交換および交流の場を通じた調査、資料収集】 (1) 「河川文化を語る会」 「河川文化を語る会」は、川と人とのかかわりを河川文化として捉え、様々な側面からの知識を習得することや相互の交流を深めることを目的に、講師を招き、講演および意見交換の場として平成10年6月から実施しています。 (2) 地球温暖化適応策に関する調査、資料収集 地球温暖化適応策に関する基礎的な資料を収集し、ホームページに関連情報を掲載しています。 (3) 月刊誌『河川』の発刊 月刊誌『河川』は、昭和初期から現在までの、その時々の河川事業・河川行政の歴史や社会の変遷を知る貴重な資料として、行政関係者、研究者、学生、一般の方などに広く活用され、高い評価を得ています。 月刊誌『河川』(昭和17年~)およびその前身である『水利と土木』(昭和3~16年)の目次および最新号までの本文記事をホームページで公開しています。記事は、発行年月、題名および著者のキーワードで検索でき、昭和初期から現在までの約80年間にわたる日本の河川事業の経緯と河川行政の歴史を知ることができます。記事の閲覧は、一種正会員(地方公共団体等)、二種正会員(個人会員)および三種正会員(法人・企業)の皆様が可能です。 (4) 河川情報の資料収集・解析 河川に関する様々な情報を収集・整理し、情報発信に努めています。 【安全かつ快適で自然豊かな河川を実現するための調査、資料収集】 (1) 「川の日」キャンペーン 「川の日」実行委員会が実施する「川の日」記念行事を事務局として支援しています。「川の日」の7月7日ごろに、商用Webサイトにバナーを掲載し、これにリンクして様々なコンテンツを広く一般に提供し、「川の日」の啓発を図っています。 (2) 水防演習に参画 全国の会員の皆様のご賛同とご支援を得て、出水期前の5月から6月の水防月間に開催される水防演習に参画し、冊子『自分の命を自分で守るために』を作成・配布するなど、一般の方々の防災意識向上のためのキャンペーンを実施しています。 (3) 河川関係キャンペーンに参画 河川愛護月間、水の週間のキャンペーンに参画します。 (1) セミナーの開催 水防に関する制度・法律等をテーマにした「水防研修」、河川管理・訴訟等をテーマにした「河川管理研修」、河川計画・技術等をテーマにした「河川講習会」を開催し、専門的知識の普及を図っています。
一般財団法人河川技術者教育振興機構が行う講習会等への支援を行います 。 (1) 河川功労者表彰の実施 昭和24年(1949年)に創設以来、治水・利水・環境の観点はもとより、歴史・文化、河川愛護、国際貢献、学術研究、地域振興等の観点から、広く社会に対して功績のあった個人や団体を表彰しています。 【河川功労者名簿】 ・「日本水大賞」は、日本水大賞委員会(名誉総裁:秋篠宮皇嗣殿下、委員長:毛利 衛)を実施主体として、水循環の健全化と水防災に貢献する様々な活動を支援する目的で、平成10年に創設され、日本河川協会は事務局として支援をしています。毎回全国から多数の応募があり、厳正な審査によって受賞者が決定されます。表彰式は名誉総裁である秋篠宮皇嗣殿下のご臨席をいただき、受賞者をはじめ多数の関係者が参加して盛大に開催されています。 ・「日本ストックホルム青少年水大賞」は、2001年から日本水大賞の一環として設けられ、毎年夏にスウェーデンで開催される、若い研究者を対象とした国際コンテスト「ストックホルム青少年水大賞(Stockholm Junior Water Prize)」に派遣する日本代表を選考しています。2004年の日本代表である「沖縄県立宮古農林高等学校環境班」は、アジアで初めてグランプリを獲得、2006年の代表「京都府立桂高等学校草花クラブ」と2018年の代表「青森県立名久井農業高等学校 TEAM FLORA PHOTONICS」がそれぞれ準グランプリを獲得しました。さらに、2020年には「青森県立名久井農業高等学校 Treasure Hunters」が16年ぶりにグランプリを獲得しました。 日本水大賞は、毎年7月7日(川の日)から10月31日まで募集を行い、翌年3月末から4月上旬に各賞を発表、6月または7月に表彰式を開催しています。 6.会員活動への助成、会員への情報誌の配布、河川関係諸団体の活動への支援 【会員活動助成等事業】 (1) 会員活動への助成 会員の親睦、交流およびサークル活動をより一層推進させるため、現在13の府県で設立されている会員組織を支援し助成を行うとともに、未設立の都道府県には会員組織の設立を働きかけていくとともに、会員が各地域において、川をテーマにした自主的な研究や地域活動への参加を行うサークル活動に対して、その経費の一部を助成しています。
会報『河川文化』(平成10年4月創刊,年4回発行) は、「川における様々な文化」をテーマに全国各地からの情報を発信する会員向けの情報誌で、無料配布を行っています。 【特 集】
会報『河川文化』のバックナンバーを閲覧することができます。 第1号(平成10年発行)から最新号まで、全ての記事が検索できます。これまでに集積された膨大な記事の中から必要とする情報を選び出せます。 「閲覧サービス」・「記事検索」ともに、対象は一種正会員(地方公共団体等)および二種正会員(個人会員)の皆様です。 河川に関係する諸団体が行う公益的な活動に対して、支援・協力をしています。 |
|
日本河川協会は、昭和15年に全国的な大水害が頻発する悲惨な状況の中で、水害を防除するためには河川に関する国民の認識を深め、官民の一致協力が必要であるとの見地から、全国の都道府県の要請と支援を受けて設立されました。 当協会は、このような長年にわたる成果を踏まえ、国民にとって安全かつ快適で自然豊かな川づくりのために、平成9年12月に定款を変更しました。これは、近年各種の環境問題が地球規模へと拡大する状況の中で、河川に対する自然志向が一段と強まり、その一方で様々な河川利用に対する要望も強くなってくるなど、河川に対する社会的関心の高まりに並行して地域住民や地域団体による川にかかわる諸活動が活発化してきたことが背景になっています。今後の協会活動は、従来の河川事業促進活動に加えて、多くの方々に個人会員になっていただき、全国的規模で河川文化の発展のために幅広い活動を展開していこうとするものです。 【 主な沿革 】
|
|
現在の役員は、会長1名、副会長2名、理事19名(専務理事、常務理事を含む)、監事2名で、任期は2年です。
|
||||||
入会をご希望の方は、入会申込書を郵送またはメールで当協会まで送付してください。 |
| 当協会の公益事業へのご寄附には、税の優遇措置が受けられます。 |
|