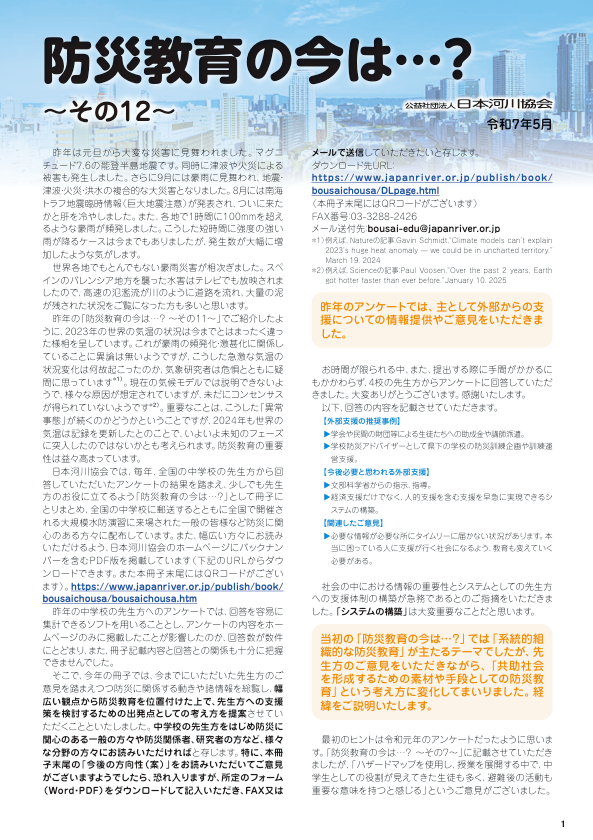 日本列島は災害列島とも言われています。地震、火山噴火をはじめ、洪水・高潮や土砂災害、豪雪、竜巻、あるいは熱波や干ばつなど、あらゆる自然災害の脅威とともに私たちは生きていかなければなりません。
日本列島は災害列島とも言われています。地震、火山噴火をはじめ、洪水・高潮や土砂災害、豪雪、竜巻、あるいは熱波や干ばつなど、あらゆる自然災害の脅威とともに私たちは生きていかなければなりません。
昨年の令和6年を振り返ってみても、数多くの災害が発生しています。1月1日の元旦からマグニチュード7.6の能登半島地震の発生、台風5号や台風10号に伴う大雨、7月に秋田県や山形県を中心に被害をもたらした記録的な大雨、そして、能登半島地震の被災地を襲い、複合災害を引き起こした9月の記録的な大雨、11月に入っても奄美地方と沖縄本島地方では記録的大雨となるなど、全国各地で甚大な被害が発生しました。
また、8月8日の宮崎県の日向灘で発生した地震では、最大震度6弱を観測し、南海トラフ地震臨時情報が運用開始以降初めて発表されました。
(詳しくは「自分の命を自分で守るために【令和7年度版】」をご覧ください)
ところで、こうした自然災害は、断層やマグマといった地表下の現象に関係するものと、大気や水が関係する気象現象によるものとに大別できるように思います。
このうち気象に関係する自然災害を考える場合には「気候変動」の影響が重要な意味を持ってきます。
例えば、洪水に関する気候変動の影響とはどのようなものなのでしょうか。2015年12月の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議でパリ協定が採択されました。気温上昇を2℃に抑えるとともに1.5℃を目指して努力するというものです。気温は一日の中で変動しますし、年間を通じても変わります。この程度の気温上昇では大きな問題は生じないようにも思えます。しかし、日単位や月単位の変動を繰り返しながら全体として気温が上昇していくことで影響がでてくるのです。気候変動によって気温が高くなると大気中に含まれる水蒸気の量が増えるので、ある時に大雨が降ったとすると、その雨の量は多くなります。その結果、より大きな洪水を引き起こすことになりますが、その際、雨量の増加率より洪水流量の増加率の方が大きくなる点に留意が必要です。また、大洪水が起きる頻度が増えるのではないかとも言われています。気温上昇の影響が、雨量、洪水流量の順に増幅され、洪水発生頻度の増加も加わって、小さな気温上昇が洪水災害の程度を大変厳しいものに増大させることを想定しておく必要があるのです。
現在、社会や経済構造は急激な変化の真っ只中にあります。子供たちは、こうした変化に適応していかなければなりません。自然災害の態様も大きく変化していきます。子供たちが変化する自然災害に対して適応することを学ぶことは、自分の命を守ることはもちろん、社会・経済の変化に適応する上でも役に立つのではないでしょうか。
今年の冊子では、今までにいただいた先生方のご意見を踏まえつつ防災に関係する動きや諸情報を総覧し、幅広い観点から防災教育を位置付けた上で、先生方への支援策を検討するための出発点としての考え方を提案させていただくことといたしました。
子供たちへの防災教育の重要性に鑑み、防災教育の充実を図る一助となることを切に願う次第です。
公益社団法人 日本河川協会